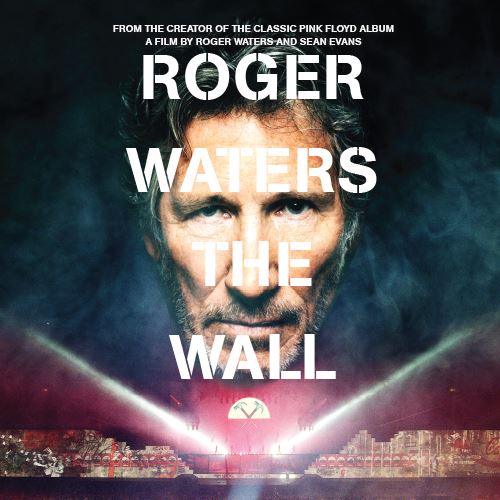「ロジャー・ウォーターズ ザ・ウォール」(2015)日本語版予告編
「どうも最近、ライブ中に観客と一体感を得られんのよ……。つーか、あいつら騒いでばっかでぜんぜん俺のことわかってくれへん。こないだなんか、ステージによじ上ろうとするアホがいたもんやから、ツバひっかけてもうた。なんでこないにしんどい目に遭わないかんのやろ。ステージと客席の間にごっつい壁ができてもうた気ぃする。……そうや! だったら演奏中にステージの上に壁を築いてやったらええんや! 連中びっくらこくでぇ」
こんなタワけた思いつきから製作されたのがピンク・フロイドのアルバム『ザ・ウォール』(1979)。実際に紙製のレンガを演奏中に積み上げ、ステージ上に巨大な壁を出現させる、ロック史上空前の規模と言われるそのライブ・ツアーがスタートしたのは、1980年の2月。そこから36年目となる今年、新たに映画として生まれ変わった『ロジャー・ウォーターズ ザ・ウォール』のBlu-rayが、ついに日本でも発売された。
とは言っても、日本盤Blu-rayはDVDとのセット商品となっているため割高だ。訓練されたフロイドファンはとっくに12月に発売された輸入盤を入手していることだろう。こちらにも日本語字幕機能はついており、内容に違いはない。
今回の『ロジャー・ウォーターズ ザ・ウォール』は、そのタワけたアイディアの主であるロジャー・ウォーターズによる、2010~13年の間に行われた「ザ・ウォール・ツアー」公演を元にしている。この公演、3年間余にわたる動員数は450万人を越え、U2の「360℃ツアー」、ローリング・ストーンズの「The Bigger Bang Tour」に次ぐ史上3番目の規模にして、興行収益は4億6400万ドル以上(日本円にして500億円強)というから凄まじい。ソロ・アーチストとしては歴代最高、あのマドンナやポール・マッカートニーをも越えているのだ。
2015年11月29日夜、『ロジャー・ウォーターズ ザ・ウォール』は、全世界の映画館で一日だけの劇場公開を果たした。
なんでまた今どき『ザ・ウォール』なのか、いったいどんなものが仕上がったのかと期待半分不安半分で観に行ったのだが……。
はっきり言う。上映終了後は最上級のパフォーマンスアートを満喫した幸福感にひたっていた。そして、この作品がたった一日の限定上映であることを心の底から惜しんだ。コンサートフィルムの可能性を広げたという枠にとどまらず、一人のアーチストの内面洞察から社会批判につながる文学的な感性、それを彩り豊かに表現する楽曲群を、秀逸なレイアウトによる撮影・編集で表現する第一級の映画だったからだ。1982年に公開されたアラン・パーカー監督『ピンク・フロイド/ザ・ウォール』はまさにアルバムの「絵解き」以上のものではなかったが、こちらは作者自身の手によって21世紀の世に向けて更新された新たなる『ザ・ウォール』そのものなのだ。
むろん、音響の素晴らしさは言うまでもない。ドルビー・アトモスの特性を駆使してライブ会場の臨場感を見事に再現している。ちなみに音楽プロデューサーとして雇われたのは、レディオヘッドを長年手がける、ナイジェル・ゴッドリッチだ。
終映後、仲間を連れて観に来ていたあるベテランミュージシャンが、出口に向かいながらこう呟いていたのが忘れられない。
「究極だね!」
そう、『ロジャー・ウォーターズ ザ・ウォール』は『ザ・ウォール』の、そしてロック・オペラというジャンルの究極形態なのである。
さて、英米では『狂気』とならぶピンク・フロイドの名盤とされる『ザ・ウォール』だが、初演ツアーでもロジャーのツアーでも来日公演が行われなかったこともあり、日本ではもうひとつ認知度が低いようだ。また、フロイドファンの間でも評価が分かれるアルバムでもある。初期ピンク・フロイドの幻想性、甘美なけだるさ、遊び心に満ちた音響世界を愛するファンほど、『ザ・ウォール』に対する評価は厳しい。曰く、「説明的な上に説教臭い」、「大げさで陳腐」、「音楽的に地味」、「ロジャーのエゴイズムに辟易」……。
それらの批判は、じつはどれも当たっている。
が、それはキリンに向かって「首が長過ぎる」という類いのもの。そうした弱点を越えて『ザ・ウォール』という作品が愛聴され続ける理由を、映画『ロジャー・ウォーターズ ザ・ウォール』は示しえているのではないだろうか。
もっとも、『ザ・ウォール』はステージ・ショウを念頭に製作されているため歌詞が多く、そのくせ難解で、いくら歌詞カードと首っ引きでアルバムを聴き込んでも、英語圏でない者には内容を把握しづらい(英語圏の人でも難しいらしい)。早い話、「小難しくてワケわかんない」という印象を持たれやすいのだ。まずいことに『ロジャー・ウォーターズ ザ・ウォール』でも、ロジャー自身が演じる「旅」のパートで交わされる会話には日本語字幕が出るのだが、ステージ上で歌われる歌詞に日本語訳は出ない。不幸にもあなたがまだ『ザ・ウォール』というアルバムを聴いたことがなければ、『ロジャー・ウォーターズ ザ・ウォール』を観ても、ステージで展開する内容が理解できず、困惑してしまうかもしれない(もちろん白紙の状態で観ても、言語がわからなくても、じゅうぶん楽しめるはずだが!)。
そこで、今回は『ロジャー・ウォーターズ ザ・ウォール』をより深く味わうため、改めてオリジナルの物語を確認し、今回の映画版ではどのような演出が追加され、いかなる変身を遂げたかを確認してゆこうと思う。
まずは、オリジナルの『ザ・ウォール』のあらすじを紹介しよう。
(第1部)
主人公は、ピンク・フロイドという名のミュージシャン。熱狂的なファンを多数持つポップスターだが、すでにプレッシャーによって精神は荒廃し、ホテルに引きこもっている。数時間後に公演を控えたピンクは、自分がファシストの独裁者となって観客を挑発する夢のステージを空想する。そんなピンクが生まれたのは第二次世界大戦の時代。出征した父はイタリアで戦死したため、ピンクは父の顔すら見たことがない。父親不在の孤独な少年時代を送ったピンクは、学校では高圧的な教師にいじめられ、家では過保護な母親に監理されて育ったため、いつしか心に「壁」を築きはじめる。
成長し、ミュージシャンとして成功するピンクだったが、ポップスターらしく酒と女に溺れ、結婚しても妻とは信頼関係を築くことができなかった。ある夜、公演先から自宅に入れた電話で妻の浮気を知ったピンクは、ホテルに連れ込んだグルーピーの前で狂乱し、手当り次第にものを破壊する。そして心の壁に最後のレンガをはめこみ、現実世界との交わりを拒否するのだった。
(第2部)
壁の中で自閉するピンクは、現実との接点を見出そうとするものの、すでに壁はあまりにも高く、孤立無縁の状態となっている。少年時代の回想とホテルでぼんやりテレビを見る現実が入り乱れ、ピンクの心はじょじょに崩壊してゆく。
しかしステージは開演直前、ホテルのドアを壊して入りこんだマネージャーや医師たちがピンクに気付け薬を注射する。薬物の浮遊感に酔い痴れながらステージに現れたピンクは、自分が独裁者であり、聴衆はその信奉者だと思い込む。そして気に入らない観客やマイノリティに対するヘイトスピーチをぶちかまし、恐怖政治によって世界を支配する自分の姿を幻視する。
そこへ、唯一残っていた良心がピンクの行動を制止する。ピンクは意識下で自らを裁く裁判を開廷する。証人として現れる教師、母、妻たちは次々とピンクに不利な証言を重ねてゆく(それらはすべて自分自身でもある)。裁判長はピンクを有罪と確定、「壁を打ち壊し、その醜い姿をさらけ出すがよい!」と宣告する。そして壁が轟音とともに崩れ落ちる。はたしてピンクは解放されたのか……。
アラン・パーカー監督『ピンク・フロイド/ザ・ウォール』(1982)予告編
ハンディキャップを負った主人公の一代記である点ではザ・フーの『トミー』(1969)の影響が感じられ、主人公の精神世界の旅を演劇的に構成する点では、ジェネシスの『眩惑のブロードウェイ』(1974)を意識しているようにも思われる。
それらロック・オペラの先行作を参考にしたことは間違いないと思うが、私の見るところでは、『ザ・ウォール』に最も近いのはフェデリコ・フェリーニ監督の映画『8 1/2』だ。『8 1/2』が、才能に翳りの見えた映画監督の現実逃避が描かれていたように、『ザ・ウォール』も行き詰まったミュージシャンの現実逃避が描かれる。いずれも一般観客にとっては「そんな泣き言、知ったことかよ!」と言いたくなる個人的なテーマである。が、その極私的な苦悩を突き詰めることで、より普遍的な共感を呼ぶマジックに満ちているのが両作品の特徴だ。
1982年に公開された映画『ピンク・フロイド/ザ・ウォール』は、この物語をプロモーション・ビデオ風の劇映画としてまとめたものだが、アラン・パーカー監督は、あまりにもロジャー個人によりかかりすぎた物語を普遍化しようと、主演にボブ・ゲルドフを迎え、歌詞のイメージをグロテスクに再現することに注力した。
しかし、ロジャーの構想では、映画版には自らが主演するつもりだったという。その上、実際のライブ映像も混ぜ込んだ虚実皮膜のスタイルでの映画化を考えていたらしい。1981年6月、映画の素材とするため、ロンドンで改めて『ザ・ウォール』公演が数回行われ、すべて撮影されたのだが、結局、ワンカットも使われず、今も封印されたままである。
また、ピンク・フロイドのアルバムとして『ザ・ウォール・ライブ アールズ・コート1980~1981』というライブ盤が2000年にリリースされているが、これもロジャーとしては不本意な企画であり、デヴィッド・ギルモアたちによって勝手に進められたものだという。
なぜロジャーは『ザ・ウォール』のライブ盤や公式映像のリリースを渋っていたのか? それは、彼にとってかつての『ザ・ウォール』公演や映画版にはまだまだ不満が多く、いずれ機会を見て、より完璧なステージとより構想に忠実な映画をまとめて完成させるつもりだったからにほかならない。
そして満を持して行われたのが2010~13年のツアーであり、今回の映画だったというわけだ。1980~81年の『ザ・ウォール・ツアー』は、装置があまりに壮大すぎたため、4都市31公演しか行われず、しかも赤字だったという。が、ハイテク技術を駆使して行われた2010~13年のツアーは全世界で219公演を行い、最大級の収益を上げた。
では、2014年に完成した映画『ロジャー・ウォーターズ・ザ・ウォール』は、1979年の『ザ・ウォール』をどのように進化させたのだろうか? 次にこの映画の展開を確認する。
<プロローグ>
映画は、黒味に鳥の鳴声がさえずっているところへ一発の銃声、そして車の急ブレーキの音で始まる。現実音による導入部という、ピンク・フロイドの定番手法は健在だ。
公演を終えて楽屋口に現れたロジャーはにこやかにローディーになにか話しかけている。彼は駐車場へと案内され、出迎えの高級車に乗り込む。向かうのは、次の公演地……ではなく「家(Home)だ」。ある洋館に到着したロジャーは、そこで父の出生証明書や死亡通知を確認する。そしてガレージにあったロールスロイスに乗り込み、戦没者墓地を訪れる。白い墓標が無数に並ぶ墓地を歩くロジャー。風に乗ってかすかに流れるメロディは、本来アルバムに入るはずだったが、尺の関係で外された「ホエン・ザ・タイガー・ブローク・フリー」(後に映画版『ピンク・フロイド/ザ・ウォール』に使用され、現在はアルバム『ファイナル・カット』に組み込まれている)。
墓地で父エリック・フレッチャー・ウォーターズの名を確認したロジャーは、おもむろにトランペットを取り出し、「アウトサイド・ザ・ウォール」のメロディを吹く。その時、大空に巨大な爆撃機が出現し……
<第1部>
ステージ上に爆撃のイメージで花火が激しく打ち上げられる。すさまじい火薬量。消防法にうるさい日本ではまず上演できないだろう。
そこで「イン・ザ・フレッシュ?」がスタート、ロジャーが姿を現す。
フロイド時代のライブでは、この曲はメンバーの仮面をかぶったサポートミュージシャン扮する偽ピンク・フロイドによって演奏された。偽物が観客を挑発し、本物のバンドメンバーが現れるのは、ピンクの誕生を表現する2曲目の「ザ・シン・アイス」から。しかし、ロジャーはすでにピンク・フロイドではないので、ソロツアーのライブでは軍服と黒コートを着込み、ファシストスタイルで叫びまくる。
曲の最後に、ドイツの急降下爆撃機が客席の上方からステージに墜落、爆破炎上するのはオリジナルのステージと同じ。
そして2曲目「ザ・シン・アイス」へと続く。父の戦死とともに誕生した主人公。背景の円形スクリーンには、戦死した軍人、空爆の犠牲者、暗殺された平和活動家の写真が次々と映写されてゆく。つまりこれは主人公=ロジャーの物語であると同時に、不条理な暴力で家族を奪われた者の物語なのである。
一方、父の墓参を終えたロジャーはふたたび車に乗ってドライブを開始する。ステージのライブ映像と、ロジャーが自分の「原点」を確認する旅が交錯する構成だが、どうやらこのライブ映像は旅するロジャーの内面描写として展開しているらしい。もはや「ピンク」という架空のミュージシャンを彼が演じる必要はなくなっているのだ。読みかけのガブリエル・シュバリエ『恐怖』(第一次大戦を描いた戦争文学)に挟んだ母宛の手紙を取り出すロジャー。そこには、戦友による父の死亡状況が詳述されていた。
父親不在で育った少年時代を思い起こしたからだろう、ステージでは「ザ・ハピエスト・デイズ・オブ・アワ・ライヴズ」から「アナザー・ブリック・イン・ザ・ウォールPart2」へと続き、巨大な「教師」の怪物がステージに登場して体をクネクネと動かす。「教師」はコンピュータ制御された宙吊りのロボットだが、技術の進歩は素晴らしく、フロイド時代のものよりはるかによく動いているようだ。そこへローティーンの子供たちがだーっとステージに現れ、ダンスをしながら「Hey,teacher! leave then kids alone!(やい先公! 子供たちを自由にさせろ!)」と教師ロボに悪態をつく。これは公演地を移動するたびに地元の子供たちに参加してもらっているそうだ。彼らの着るTシャツには「Fear builds wall(恐怖が壁を築く)」の文字がプリントされている。
そして、このあたりからレンガの組み立てが始まる。このパフォーマンスで組み立てられる「壁」とは、心の壁だけでなく、パレスチナにおけるガザの壁のような、人種の「区分け」に代表される現実の障壁をも指している。
そこへ銃声がつんざき、地下鉄がすべりこんでくるアニメが映写される。2005年にロンドンの地下鉄駅で自爆テロ犯と間違えられ、警官に射殺されたブラジル人、ジャン・チャールズ・デ・メネゼスへの追悼ソングをせつせつと歌うロジャー。「高圧的な教師」は「移民を射殺する警官」へと拡大されたのだ。こういうイギリス人でなければとっさに理解できないネタを堂々と突っ込んでくるのもロジャーらしい。
ロジャーのフランス語によるMCの後(映像を収録したのはヨーロッパ数カ国での公演)、「マザー」が演奏される。フロイド時代のライブと同じく巨大な「母親」の像が登場するが、監視カメラのように目がサーチライトとなって光るのが面白い。「過保護な母親」も、「監視する政府」へと意味合いが広げられている。ステージ上には1980年のライブ映像が映写され、36歳のロジャーと70歳になるロジャーがそろってこの曲を歌う。
さて、ドライブを続けるロジャーの車には、いつのまにか助手席に一人の友人が乗っている。クレジットによると彼は宗教学者にして哲学者のアンドリュー・ウィル・ローリンソン。高校生のころ、ロジャーは同級生だったローリンソンとともにヨーロッパを縦断し、中近東まで旅をしたという。
ここでロジャーがあるロシア映画の話題を振るが、これはニキータ・ミハルコフ監督『ウルガ』のことである。この話題をきっかけに、ロジャーは自分の祖父について語り出す。なんと、ロジャーの祖父ジョージ・ヘンリー・ウォーターズもまた、ロジャーの父エリックが2歳の時に、第一次大戦の戦場で戦死していたのだった。
祖父の墓を、ロジャーと3人の子供たちが訪ねている。今回の『ザ・ウォール・ツアー』ではハモンド・オルガンを担当している長男ハリー、モデルとして活動する長女インディア、まだ10代の次男ジャックだ。祖父・父二代に渡って兵士として国に命を消費されてしまった家族。立ちならぶ白い墓標のイメージから、ステージ上で演奏される「グッバイ・ブルースカイ」へとつながってゆく。スクリーンに映写されるのは新作のアニメ映像で、青い空を引き裂いて現れる爆撃機の腹から無数の$マークや三日月、ダビデの星、さらにシェル石油やベンツのマークがバラバラと落ちてゆく。現代の戦争の背景に宗教や資本主義経済がからむことへの諷刺である。
ジェラルド・スカーフによる「愛を交わす花」
続く「エンプティ・スペース」では、オリジナルのツアーでも使用された、諷刺漫画家ジェラルド・スカーフによるアニメ「愛を交わす花」が上映される。もつれ合い、からみ合い、やがてお互いを喰らい合う男女の花のアニメ。さらに、「ヤング・ラスト」からはステージ上の壁にさまざまな女性のイメージが映写され、性的な雰囲気が高まってゆく。同時に、壁のレンガもじょじょに高く積み上げられてゆく。
ステージでセクシャルな演出が進行する一方、映画のカメラは洋館の中を一人称視点でぐるぐると彷徨する。ロジャーは旅を続けながらも「出口なし」な気分に苛まれているようだ。そんなロジャーに、同行するローリンソンはかつて共に旅をした際、ギリシャで雷に打たれて神秘体験を得た話をするのだが、ロジャーにはそんな記憶はまったくない。一方でロジャーは「父殺し」の夢を見た話をする。人間が享受すべき幸福感についての会話を交わしながら旅を続ける彼らの車は、荷馬車を引く難民らしき一家のそばを通り過ぎる。
そこへ、衝撃音! ステージ上の壁に映写された政治家たちの映像に亀裂が入るモンタージュが炸裂する。現実の紛争や貧困問題を解決するどころか拡大する一方の政治家への怒り爆発、さらに黒人男性を袋だたきにする警官の映像まで重ねられ、歌詞の暴力感情を表現する。そこから巨大な壁を棒高跳びで越えようとする男のイメージや、ヘリコプターのノイズなどが複雑にモンタージュされ、ギターのフレーズが執拗にくり返される。壁が完成するまでの緊張感を高めるために新しく作られたパートで、「ラスト・フュー・ブリックス」と名付けられている。
ステージ上には壁が高く築き上げられ、最後に残った壁の穴から顔をのぞかせたロジャーが「グッバイ・クルエル・ワールド」を歌う。終わると同時にレンガがはめこまれ、巨大な「壁」が完成する。この流れはフロイド時代のライブと同じだ。
<第二部>
ロジャーはフランスのホテルのバーで一杯ひっかけている。英語がわかってなさそうなバーテンに、「これからイタリアに行くつもりだ」と心境を語る。父エリックはイタリア・アンツィオ海岸上陸作戦に参加して戦死した。彼はその現地を訪れるつもりなのだ。そんなロジャーの前に、ハンガリー人の男が現れ、1944年、7歳の時にナチスに追われて国を脱出したエピソードを語る。この映画における「壁」とは、自閉した精神やコミュニケーションの障壁だけでなく、「国境」をも意味しているのだ。映画では何の説明もなされないが、このハンガリー人とは『チェンジリング』や『蜘蛛女』を撮ったピーター・メダック監督である。
さて、ステージでは後半戦1曲目の「ヘイ・ユウ」が始まる。自閉した状態で鬱に苦しむ心情をせうせつと訴えられても、観客は高い壁に阻まれ、バンドの演奏を見ることができない。ナチズムから脱出したハンガリー人と違い、壁を築いてしまった者に逃げ場はないのだ。
やがてその壁に人間の両目のアップが映し出され、「イズ・ゼア・エニバディ・アウトゼア?」(誰かそこにいるのか?)とうめき、壁の一部に穴が空く。デイヴ・キルミンスターとG.E.スミスの二人が美しいギターを奏でる。そして、ホテルの一室にいる孤独な主人公が、戦争映画を見ながら「ノウバディ・ホーム」を歌うのは、オリジナルのステージと同じ演出だ。
ロジャーとローリンソンのドライブはまだ続いている。そこでロジャーは「ライブの時には毎回20人の傷痍軍人を招待してるんだが、ある時、その一人が俺の手を握って『君はお父さんの誇りだ』と言ってくれたんだ」と話す。さすがロジャー、こんな時にも自慢話を忘れねぇなぁ、と思いきやステージでは「ヴェラ」が演奏され、壁には兵士が家族の元に帰還する瞬間のドキュメント映像が映される。「また会いましょう」という歌で知られる出征兵士のアイドル、ヴェラ・リンに向かって「そんなこと言ったくせに俺は親父に会えなかったぞ!」という恨み節。続いて「製造されたすべての銃、出征したすべての兵士、発射されるすべてのロケット、これらはすべて服もなく寒さに震える人々からの窃盗によって成立する」というアイゼンハワー大統領の言葉が堂々と映し出される。
さて、イタリアはアンツィオの海岸に到着したロジャー。父が死んだ海を、一人言葉もなく見つめ続ける。そのかすむ水平線がステージに重なったところで、有名曲「コンフォタブリー・ナム」がスタート。歌詞に出てくる水平線のイメージとうまくかぶせた構成だ。往年のライブでは、ロジャーはこの曲になると白衣を着て医者の扮装をし、でかい注射器を壁に打ち込んだりしたものだが、今回はそういう演技はしない。壁の頂上に立ったデイヴ・キルミンスターがギルモアばりのギターをかき鳴らすと、ロジャーは派手に壁を両手で叩く。するとアニメの壁が粉々に崩壊し、サイケデリックな色の奔流が展開するのだ。
薬物の力で幻想の「解放感」を得たものの、途方もなく孤独な魂の持ち主が惹かれてゆくのは、ハンマーの旗印と黒シャツ隊によって覆われたファシズムの世界だった。巨大な黒ブタの風船が現れ、会場の上空を飛びながら観客を睥睨する。皮のコートにサングラスを着て独裁者へと変身したロジャーは差別主義者のパロディソングである「イン・ザ・フレッシュ」を歌い、「できることならお前らみんな撃ち殺してやる!」の部分で観客に向けて機関銃を撃ちまくる。
続けて始まる「ラン・ライク・ヘル」、この時、ロジャー総統は客席に向けてMCを始める。
「この中に偏執狂はいるか? 聞け! これはお前らの曲だ! さぁ手拍子を! 俺について来い!」
フロイドやロジャーのライブでは基本絶対やらない、というか今でもオールド・プログレファンの間では「御法度」とされている観客への手拍子要請。これをぬけぬけとやってのけるわけだが、演奏されるのはファシズムへの服従を要求するロックンロールという皮肉。
と同時に、背後の壁に文章が映される。日本語字幕では「ジョセフはなにも悪いことをしてないのに逮捕された」と出るので脱力するが、もちろんカフカの『審判』の冒頭、ヨーゼフ・Kの逮捕を書いた一文である。さらに、オーウェル『1984年』の一文などが映写される中、ステージは「赤」を貴重にしたデザインとライティングでファシズム讃歌が妖しく煽り立てられる。中間部のリフはアルバム以上にたっぷり引き延ばされ、毛沢東やヒトラーといった独裁者たちや、米軍ヘリがイラクの住民を射殺する映像などが映し出される。
ジェラルド・スカーフによる「ハンマーの行進」
そして『ザ・ウォール』で最も有名なジェラルド・スカーフのアニメ「ハンマーの行進」が映し出され、ロジャー総統はメガホンを使って親衛隊の行進を鼓舞する。この光景、日本でも「在特会」の登場によってすっかり理解しやすいものになってしまった。
熱狂が最高潮に達したところで、「ストップ!」の声がかかり「ザ・トライアル」へと移行する。この裁判劇パートはさすがにオリジナルとまったく同じで、ジェラルド・スカーフによるアニメーションが壁に上映され、検事、教師、母、妻、裁判官、そして被告の主人公を声優ロジャーが一人で演じる。
クライマックス、裁判長の「壁を打ち壊せ!」の一声で、ステージ上に構築された壁が轟音とともにいっせいに崩壊する。大スペクタクル場面だが、どういう仕組みになっているのか、レンガたちは自重により自然崩壊してゆくように見える。「障壁が除去される」というよりは、「躁状態のアッパー感覚から鬱状態のダウナー感覚への変化」、という方が印象としては近いのだ。
<エピローグ>
ロジャーの旅も、最終地点に到着した。イタリアで戦死者の記念碑を見物したロジャーは、そこに「エリック・フレッチャー・ウォーターズ」の名が刻まれているのを発見する。イギリスで見つけた名前が、イタリアにも存在した。そうした痕跡を探し求め、得ることのできなかった父親からの愛情を追体験する行為は、いつしか終わりを迎えることがあるのだろうか? 彼はここでも、トランペットを取り出し、「アウトサイド・ザ・ウォール」を吹く。すると、戦死者慰霊墓地のロングショットが、終演後のステージへとオーヴァーラップしてゆく。
ロジャーをはじめ、メンバーが舞台袖からカーテンコール風に登場する。これはオリジナルと同じだが、崩壊した壁の向こう側から「帰還」するのではない、というのが重要である。めいめいマンドリンやタンバリンを持ち、楽しげに「アウトサイド・ザ・ウォール」を歌い、演奏しながら消えてゆく。『8 1/2』のラストシーン、全登場人物による輪舞とよく似ている。崩れた壁の向こうに見える円形スクリーンには、両手を広げた少女のシルエットが映写されている。
メンバー紹介を終え、満足そうなロジャーが舞台裏に引っ込み、ローディーになにか話しかけたところでプツン、と映画も終わる。きっと彼の行く手にはまた出迎えの高級車が用意されているのだろう。ちなみにアルバムでは「Isn't this where we came in?(始まりはここから?)」というセリフがアルバムの出だしと最後で分割されている。
エンド・クレジットには、ロバート・キャパやゾフィー・シェルといった有名人から身元不明の学生まで含めた、さまざまな国での戦争犠牲者のポートレートが浮かんでゆく。
『ロジャー・ウォーターズ ザ・ウォール』(2015)より〜第1部冒頭の「イン・ザ・フレッシュ?」
ながながと、映画の展開を紹介してしまったのは、今回の構成演出の特徴を簡単に説明すると、
「なるほどー、ロジャーは今じゃ平和活動家だから、個人的な鬱状態を描いていた作品を、反戦、反権力というテーマに大きく昇華させたんだなぁ」
と、安易に解釈され、思想面のみで感心したり反発したりしてしまう人が多いのではないかと心配したからだ。確かに、「戦争」というコンセプト設定は、『ザ・ウォール』を21世紀のエンターテインメントショーにアレンジする上での重要な要素ではあるし、ロジャーはフロイド時代から筋金入りの自由主義者である。
が、『ザ・ウォール』はそもそもロックコンサートというイベント自体が、安易にファシズムやプロパガンダに取り込まれやすいものであることを批評的に内包した作品だ。反戦メッセージだけ訴えたいであれば、大金をかけてこんなショーをやらなくてもチャリティーで充分だし、なにも黒塗りの高級車で欧州を旅しなくたってよい。
改めて、『ザ・ウォール』が冗談のような思いつきから出発したことを思い出そう。ロジャーの観客への被害妄想から始まったこの作品は、他者への脅威とその克服をめぐる内省的なドラマとして完成した。
しかし、オリジナルの『ザ・ウォール』公演では、バンド作品である以上、最大の協力者であるギタリスト、デヴィッド・ギルモアをフィーチャーしなければならない事情もあったし、薬物に溺れてゆくミュージシャンという主人公ピンクのイメージには、ピンク・フロイド初代リーダー、シド・バレットが投影されるなど、ロジャーの私物と言い切るにはためらいの残る要素が数多くあった。
『ロジャー・ウォーターズ ザ・ウォール』は、その題名通り、作品世界から夾雑物を排除し、『ザ・ウォール』という作品が築く世界感を、完全にロジャー個人の、二代に渡って「国家」から肉親を奪われ続けた家族の、白人のポップスターが世界の紛争や貧困に思いを馳せることがどこまで可能かを思索する男の、老いてなお幼少期のトラウマにとらわれ続ける者の、「旅をしながら見る夢」として視点を設定し直し、全世界に向けてショウアップする、きわめてバロック精神に富んだ映像パフォーマンスなのだ。
この映画には、大きな建造物が構築されてゆくのを見る楽しみもあれば、それがぶち壊されるのを見る楽しみもある。そしてなにより「車が走る映画」である。容貌魁偉な黒服の大男であるロジャーが、黒塗りの高級車を運転してヨーロッパの道を走る映像とライブステージの熱狂の交錯、これがショーン・エヴァンズによるまったく隙のないレイアウトで捉えられる。
視覚・聴覚への快さに満ち満ちたイメージの大伽藍として、心ゆくまで堪能してほしい。
なお、ロジャー・ウォーターズは1992年の『死滅遊戯(Amused To Death)』以後、ロック音楽の新作アルバムはないが、2005年には17年越しの大作オペラ『サ・イラ~希望あれ』を完成させている。これは、フランス革命を題材に、ブリン・ターフェル、イン・ファンら一流歌手を集めた本格的オペラだが、なにしろ円形劇場様式による上演を想定しているので、完全な形での上演はまだなされていないはずだ。おそらく、ロジャーは長年に渡ってこのオペラと格闘し、上演のアイディアを夢想しているうちに、『ザ・ウォール』を更新する自信を得たのではないだろうか。
自らが「最高傑作」と認める自作を完全に満足の形にいくものに仕上げる愚直な執着心と、そのために費やされた膨大なカロリー。これぞ「コンセプト・アルバム馬鹿一代」の集大成にして白鳥の歌……と言いたいところだが、これまた15年ほど前から噂されている新作アルバムがいよいよ完成間近とのこと。すでに72歳、『ザ・ウォール』発表時の倍の年齢となったロジャーの「晩年様式」はいかに。