
公式サイト http://www.pref.ishikawa.jp/shiko-kinbun/
今月の初め、金沢に行ってきた。
金沢の町を歩くのは十数年ぶりだ。さすがに2月の金沢は寒い。が、北陸新幹線の開通を控え、静かに力をためる街の息吹が感じられた。小料理屋の店主に聞くところによると、観光客をさばくホテルの数が足りなくなっているという。
石川近代文学館は、初めて訪れた。かつては旧制高校だったという煉瓦造りの巨大な建物だ。ここでは、先月から企画展「彷徨の作家 島田清次郎」が開催されている。
島田清次郎(1899〜1931)、と言ってもこの名を知っているのはマニアックな日本文学ファンに限られるだろう。
1919年(大正8年)、金沢出身の島田清次郎・通称「島清」は長編小説『地上』を新潮社から出版し、20歳で作家デビュー。極貧の文学青年はまたたくまに大ベストセラー作家へと成長し、『地上』シリーズ四部作は累計50万部という驚異的な売上を記録した。「天才」の名をほしいままにした島清は勢いに乗って洋行、アメリカからロンドン、パリ、ベルリンを訪れ、詩人エドウィン・マーカム、作家ジョン・ゴールズワージー、俳優の早川雪州らと面会している。全国で講演活動を行っては英雄的な理想主義、革命思想を賞揚し、テレビ・ラジオのない時代において十代の少年少女たち憧れのカリスマとして君臨した。
が、現代の目で見て島清のユニークな点と見なされるのは、その作品ではなく、尊大な言動と傲慢さが服を着て歩いているような生活態度、つまりキャラクターであった。
全盛期における発言の一部をTwitterの島田清次郎botから引用すると、ざっとこの調子だ。
日本全体が己れに反対しても世界全部は己れの味方だ。 世界全部が反対しても全宇宙は己れの味方だ。 宇宙は人間ではない、だから反対することはない。 だから、己れは常に勝利者だ。
何かしらんが、この島田を絶大なる何ものかゞ守つてゐるやうだ。自分はその大きなもの――社会、世界、宇宙――に守られつゝ、宇宙の力を養分として自分の授かつて来た高貴なるものと共に生長してゆく。
諸君は眼を双手で蔽うて、「太陽が出なくてはならぬ」と言ふけれど、太陽は出てゐるのだ。「己れ」と云ふ若き太陽が出てゐるのだ。眼をひらいてよつくみるがよい。
人類十七億、ことごとく死物で、私一人が生きてゐて、怪物の名をほしいまゝにするのは、ちと、身に過ぎた贅沢のやうな気もする。ハハ。
島田清次郎と志賀直哉とどちらが差別的であると云ふのか、そんなことは分り切つたことだ、志賀なんぞ島田清次郎の一小部分ぢやないか、このことは今でも分る者には分るが、今に尚よく分る。見てゐろ。
生来自分は女には愛される方の質であると信じ、又自分を愛さないやうな女は盲か何かであらうと自惚れている。
芸術に興味ある彼の国々の王子や貴族達が、今、日本にどんな芸術があるかと尋ねた場合、『我が親愛なるプリンスよ、われわれの国には島田清次郎がゐて、『地上』と云ふ創作を出してゐる、そして、彼れは、追つてわれわれ一行の後より、卿等の国を訪れるであらう。』と、答へることを忘れたまふな。
現在、Twitterやブログでこんな文章を年中書き散らしている作家がいたら、「イタすぎる奴」として嘲笑され、誇大妄想狂と見なされること確実だろうが、これが島清の日常的思考なのであった。
なにしろ愛読者を前にして「俺はマンではなくキングだ」とのたまい、日本における「精神界の帝王」を自称した男である。
ところが、増長した島清はファンレターの交換をきっかけに知り合った海軍少将の娘・舟木芳江との結婚話を強引に進め、彼女を連れて逗子の旅館に宿泊したところ、舟木家から拉致監禁で訴えられてしまう。
天才作家と少将令嬢のスキャンダルということでマスコミは二人の記事を面白おかしく書き立て、大騒動へと発展した。告訴は後に取り下げられたものの、島清の名声は一気に悪名へと転じ、原稿の受け取りも拒否されてしまう。そこへ関東大震災が起こって自宅倒壊。金沢へ戻った島清だが、すでに洋行や弁護士費用で印税をあらかた使い果たしていたため、一年もたたぬうちに経済的困窮に陥る。金策のため上京、知人の家を転々としては夜露をしのいでいたところ、不審者として警察の職務質問を受け、精神科医に「早発性痴呆(現在の統合失調症)」と診断されたのが運の尽き。そのまま巣鴨の精神病院に7年も収容され、退院を許されぬまま31歳で死亡した。
同じ金沢出身である杉森久英は、島田清次郎の伝記小説『天才と狂人の間』(1960)を書き直木賞を受賞している。杉森本を素材に森田信吾も伝記マンガ『栄光なき天才たち』で島田清次郎を採り上げた。また、1995年には早坂暁脚本・久世光彦演出のドラマ『涙たたえて微笑せよ〜明治の息子・島田清次郎』が放送。そして2013年には精神科医・風野春樹による最新評伝『島田清次郎 誰にも愛されなかった男』が出版された。
私が島田清次郎の名を知ったのは、吉村公三郎監督の映画『地上』(1957)を観たのがきっかけだ。映画は吉村の代表作のひとつだが、原作を書店で見かけたことはなく、なんとなく島清の名を記憶していたところ、数年後にドラマ『涙たたえて微笑せよ』が放送されたのだった。ドラマでの島清役は本木雅弘。清水美砂が最初の妻・豊を、高岡早紀がスキャンダルの相手となる舟木芳江を演じた。ちなみに新潮社の社長を筒井康隆が演じていた。
本木が演じた島田清次郎は、繊細かつ臆病で、尊大な態度の裏には卑屈な精神が貼り付き、あきらかに病んでいるのに健康な英雄を志向する引き裂かれた青年として印象深かった。島清タイプの「自意識」の怪物は、知人の中にも似たようなのが何人かいたし、自分の内部に潜む狂的な部分にどこか近しいものを覚えたため、作品を集めたり、関連資料を収集したりもしていた。だから、今回の展示もぜひ見ておきたかったのである。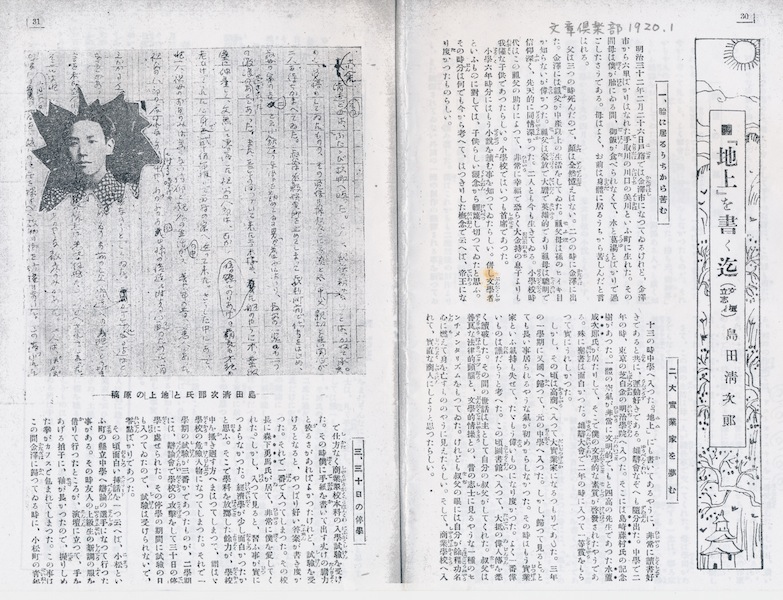
「『地上』を書く迄」文章倶楽部1920年1月号 『地上』の原稿の一部が掲載
展示はまず『地上』コーナーに始まる。島清は文学に出会う以前から「偉くなる」という観念に取り憑かれた少年だったが、小説の道に向かったのはドストエフスキーとの出会いであり、思想的にはニーチェから強い影響を受けている。
『地上』は、『ジャン・クリストフ』的な偉人成長譚を志向して書かれたらしいが、19歳の若者がそう偉大な人物の生涯を描ききれるはずもなく、内容的には自らの生い立ちを素材にふくらませたものだ。大河平一郎という遊郭育ちの中学三年生が、母と因縁のある実業家・天野栄介という傲慢な男を反面教師に、世に出て「格差と貧困」の解消に挑まなければと苦悩を深める一方、級友の片思いの相手である美少女と相思相愛になったりもする青春物語で、男女双方から好かれる大河平一郎とは作者の理想化された自画像である。
現代の目で見るとお話の造りはかなり安手で、仰々しい文章も目立ち、登場人物の造形があまりにフラットなのも難だが、「第一部・地に潜むもの」だけは遊郭の描写に実感がこもっていることもあり、なかなか読ませる。大正時代の「ヤングアダルト小説」と思えば、今の読者もすんなり腑に落ちるのではないだろうか。
島清は『地上』第一部をニーチェの翻訳者だった生田長江に持ち込み、彼の紹介でデビューが決まるのだが、生田が書いた推薦文がまたすごい。その一部を抜粋する。
げに、『地上』に見えたる萌芽より云へば、そこにはバルザック、フロオベエルの描写が、生活否定があり、ドストエフスキイ、トルストイの主張が、生活肯定があり、そのほかのなにがありかにがあり、殆どないものがないのである。
いくらなんでも褒め過ぎだろう。
志賀直哉や武者小路実篤ら「白樺派」の育ちのいい文学者が幅をきかせつつあった当時、彼らの作品に飽き足らないものを感じていた人々は、西洋文学志向の雄渾な長篇小説の登場をつい手放しで喜んでしまったようだ。
ちなみに映画『地上』を監督した吉村公三郎も中学時代に『地上』愛読したという。が、映画化のために読み直すと意外に幼稚な小説なのに頭を抱え、脚色の新藤兼人に物語の後半を改変させ、悲恋物語として仕立て直している。大河平一郎を演じたのは、後の某探検隊長・川口浩だ。
『地上』の第一部は現在、青空文庫で読むことができる。雄々しい美文体の迫力は、ちょっと三島由紀夫に通じるものを感じさせなくもない。書き出しは柔道初段の少年が、同学年の美少年を「稚児さんになれ」と組敷いているところへ、大河平一郎が通りかかって助けるという場面。もちろん助けた美少年と大河はその後、親友になるのだ。
『地上 地に潜むもの』
http://www.aozora.gr.jp/cards/000595/files/46166_22431.html
『地上』の草稿はひとマス一字で書かれているのだが、完成原稿は経済的に紙を節約したかったのだろう、ひとマス二文字で書かれている。こんな細かい原稿を読まされた生田長江、判読の労苦が感動にすり替わったんじゃなかろうか。島清と出会った当時の生田の年齢が37歳というのも少し意外だ。お互い若かったのだな……。
そして島清の生い立ちが書かれた年表に、学生時代の成績表。学業成績はかなりよかったようだ。洋行時に持参したトランクなどの遺品に、早川雪州と撮った記念写真もある。撮影用語で対象物の高さを整える行為を「セッシュウ」と呼び、その語源となったのは低身長で常に台を必要とした早川雪州なのだが、島清はそんな雪州よりもさらに小柄だった。
全盛期に出版された著書の数々も展示されている。『大望』、『帝王者』、『革命前後』、『勝利を前にして』。勇ましいタイトルが並ぶ。
そして、奥には舟木事件に関する資料を掲示するコーナー。事件後しばらくして、島清が舟木芳江に送った書簡も展示されている。事件当日、自分が芳江を暴行・監禁した原因を「結婚の約束を交わしたはずなのに、急にお前が反古にするようなことを言うから怒ったのだ」と説明する内容で、DV加害者に典型的な「オレは絶対悪くない、悪いのはオマエ」式の身勝手な論理が展開しているのが見てとれる。
展示の第二スペースへ入ると、舟木事件以後の資料がまとめて展示されている。中心となるのは、入院先の精神病院で書いた大量の原稿の数々。現存するのは25篇、中には、100枚を超す中篇や300枚に及ぶ長篇もある。いずれもレポート用紙のようなノート紙や、かつてと同じく原稿用紙にひとマス二文字でびっしり書き込まれ、「書く」という行為への執着を感じさせる。
獄中や精神病院で書きまくった作家と言えばマルキ・ド・サドをすぐに連想するが、島清の作品はあれほど想像力豊かなものではないようだ。が、それなりに完成されており、支離滅裂な内容ではないという。
しかし島清が入院中に書いた葉書も展示されていたのだが、こちらは政治家や作家など有名人に宛てて、自分がいかに病院内で虐待されているかの訴えが蟻のような小さな文字で余白もなく埋めつくされており、あきらかな被害妄想、常軌を逸した描写も散見するあたり、精神状態が相当に不安定だったことがうかがえる。
奇妙なのは、入院中の島清を見舞いに訪れた人は多く、レポート記事もいくつか書かれているのに、病院内での執筆活動を紹介しているものは皆無、という点だ。雑誌「悪い仲間」や友人だった佐藤春夫が入院中の島清による詩文を紹介しているが、小説を書いていたことは報じていない。それどころか病院の医師・看護師さえ彼がまともな作品を残していることにまるで気づいていなかったという。
島清の日記(現在、所在不明とのこと)をはじめ、周辺人物への取材をもとに書かれた『天才と狂人の間』でも、正気を失った葉書の文章は紹介されているが、入院中に書かれた作品群については、触れずじまいとなっている。杉森久英はおそらくこの事実を知っていたが、「天才から狂人への転落」という悲劇の図式が不明瞭になるのでオミットしてしまったのではないだろうか。
「自称天才の末路 精神病院に泣く島清君」東京1924年12月号
展示の第三スペースには、島田清次郎を採り上げた作品群がことごとく紹介されており、映画『地上』やドラマ『涙たたえて微笑せよ』の台本、マンガ『栄光なき天才たち/島田清次郎篇』の原画の数々、杉森久英の生原稿も展示されている。そして島田清次郎と舟木事件を素材にした徳田秋声『解嘲』の生原稿や、正宗白鳥『来訪者』、佐藤春夫『更正記』も並んでいる。『更正記』に関しては新聞連載中の挿絵までずらっと並べられていた。森山啓も島田清次郎を書くつもりで創作メモを作っていた、というのは初めて知った。
また、島田清次郎の詩文を壁に貼り出したコーナーもある。精神を鼓舞する率直な言葉が並んだ初期の詩から、「赤い風船」や「置き忘れたトランク」に自分を象徴させるどこか寂寥感の漂う晩年の抽象詩まで見通すこともできる。
入場者にプレゼントされる島清の詩文カードと赤い風船
昨年出た、風野春樹『島田清次郎 誰にも愛されなかった男』は、精神科医による評伝で、入院後の島清の病状に注目し「本当に狂人だったのか?」という点にかなりの分量を割いている。私は出版時に開催された著者と同じく精神科医である春日武彦とのトークショーも聴いているが、カルテも残されていない現在、島清の症状を類推するのは困難だが、これはきわめて判断の難しいケースだ、という点で二人の見解は一致していた。
まず統合失調症は治療可能な病気であり、向精神薬のない当時でも自然に回復する例はいくらでもあったそうだ。そもそも、統合失調症の症状は時代や環境によってさまざまに変化するので、「狂人」の烙印は簡単に押せるものではない。
島清の行動から察するに、彼は「自己愛性パーソナリティ障害」という特異な性格ではあった。それがスキャンダル後、少将令嬢をかどわかした悪漢として有名になり、国粋主義者からの抗議・脅迫が殺到、元来の誇大妄想癖が極端な被害妄想へと転じた可能性が考えられる。島清の原稿がボイコットされるようになったのも、こうした右翼の抗議が出版社にも寄せられたためだろう。
また不運なことに、補導時の島清を診断した精神科医・金子準二は当時、<精神病と犯罪は同朋>だの<日本共産党と精神異常は関係がある>などと書く偏見の持ち主だったという。目前に現れた「秩序の敵」島田清次郎に精神変調の兆しあるならば、治安維持の観点から幽閉処分にしなくてはならない、と考えても不思議はない。
『知の巨人 評伝生田長江』の著者・荒波力をはじめ、島田清次郎の精神病院送りは、革命思想を説く彼を危険視した国家権力の陰謀、という説を唱える人もいる。が、それには根拠が乏しく、やはり愚かな行為が集積した結果、身を滅ぼしたにすぎないのだと思う。ニーチェを誤読した島清は他者への想像力が欠如したイヤな奴であり、女性へのDV加害、性的暴行の癖は明治生まれの遊郭育ちという点を考慮しても弁護不能だ。早い話が人間のクズ。「天才」という称号に幻惑された俗物にすぎない。島清は没落前に自分が編集主幹におさまる雑誌の創刊を企画していたらしく、ゆくゆくは政界に進出するつもりだったようだ。しかし彼のイメージする社会主義形態というのは、自分一人が英雄としてもてはやされる世界なので、まかり間違って成功していたらとんでもないファシストを生んでいた可能性もある。
「天才」もどきの「狂人」もどきでしかなかった俗物・島田清次郎だが、そんな愚かな人物がメディアによって過剰に持ち上げられたかと思えば、さんざんに叩かれて精神病院送りにされるという物語が、日本人が持つある種の習性、醜悪さを抽出しているように感じられることに、今回の展示を見て気づかされた。昨年のSTAP細胞事件などに通ずる、「レッテル」に振り回され本質が二の次となる移り気な性格……。
魯迅が1921年に発表した『阿Q正伝』は村人から日々馬鹿にされているがプライドだけはやたらに高い阿Qという男が、革命に翻弄された末に無実の罪で処刑されてしまう話だが、阿Qとは魯迅が見た辛亥革命後の「愚民としての民衆」の象徴だった。まさに『阿Q正伝』が書かれたころに活躍していた島田清次郎。彼の作品とその理想は消え去ったが、存在だけは今も日本版の阿Qとして、鏡をのぞくに等しい苦味と滑稽味をもって迫ってくる。破滅型の芸術家の一生に漂うセンチメンタリズムとは異なる、自分自身にフィードバックする痛みが、彼の生涯にはあると思う。

『地上』シリーズ4冊と『我れ世に勝てり』&『我れ世に敗れたり』(復刻版)
島田清次郎が生前最後に出版した長編小説『我れ世に敗れたり』(この題は島清自身の命名である)は、新潮社から突っ返された後、別の出版社から発行された。作者はすでに入院中だったため、「序文」で出版の経緯が語られている。そこでは島清の境遇について同情的ではあるのだが、「院長の話によると著者の病気は不治だとのことである」との一文がある。
『島田清次郎 誰にも愛されなかった男』では、この一文について「できあがった本を手にした清次郎は、果たしてこの一文を読んでどう感じただろうか」とある。
会場には、病室で島清自身が所有していた『我れ世に敗れたり』も展示されていた。そして序文のページが開かれていたのだが、そこには先の一文から「不治」の二文字が削り取られているのだった。
揺れる精神状態に苦しみながら、島清は狂人のレッテルを拒否し、新たな小説や詩を書き続けていたのだ。退院できれば、彼の本当の作家としてのはじまりがあったのかもしれない。気づいた時が遅すぎ、出発し損ねてしまうところまで含めて、島清の生涯に浮かぶダメ男ぶりを、私はどうしても嫌いになりきれないのだった。  島田清次郎(1899~1931)
島田清次郎(1899~1931)