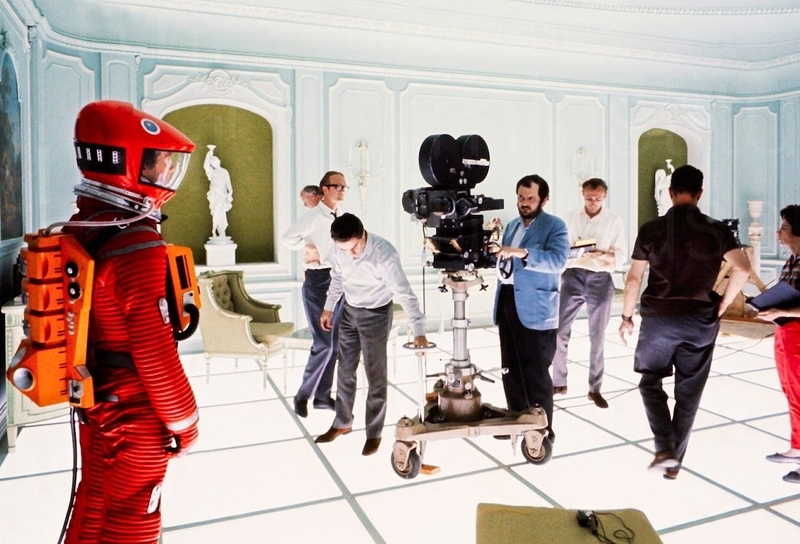「ごぶさたですね、早いものでもうベスト・テンの季節ですが、今年はいかがですか?」
「ダメですねぇ、今年はどうにか100本以上観ることができたけど、そのうち半数は旧作だし、新作も『好き』と言える作品は数えるほどしかない。ま、私がグチをこぼしながら選ぶベストテンなど世間の誰も関心を持たないだろうから、それよりもっと有意義な話をしようじゃないか。この雑誌の特集、読んだ?」
「ああ、『キネマ旬報』の1980年代の映画ベスト・テンですね。こないだ1970年代をやったから、その続きというわけなんでしょう」
「じつはキネ旬、今から28年前の1990年にも80年代の映画ベスト・テン企画を行っているんだよ」
「ほほう、1990年と言えば平成2年、終わったばかりの80年代、つまり昭和最後の10年を総括する意味もあったんでしょうね」
「平成2年と平成30年、この2種類の80年代ベスト・テンを見比べてみると、作品評価の移り変わりという点で、なかなかに興味深いのだ」
「なるほど、つまり平成が始まったばかりの1990年と、平成が終わろうとしている2018年の80年代ベスト・テンを比較してみようというわけですね」
「その通り。まずは、1990年に集計された『1980年代外国映画ベスト・テン』を見てみよう。上位20作はこの並びだった」
1990年選出 1980年代外国映画ベスト・テン
1.E.T.(1982)
2.ブリキの太鼓(1979)
3.ストレンジャー・ザン・パラダイス(1984)
4.ファニーとアレクサンデル(1983)
5.1900年(1976)
6.ダイ・ハード(1988)
7.フルメタル・ジャケット(1987)
8.ブルー・ベルベット(1986)
9.地獄の黙示録(1979)
10.ブレードランナー(1982)
11.恋恋風塵(1987)
12.ガープの世界(1982)
13.ミツバチのささやき(1973)
14.グッドモーニング・バビロン!(1987)
15童年往時―時の流れ(1985)
16.路(1982)
17.八月の鯨(1987)
18.ラストエンペラー(1987)
19.ルードウィヒ 神々の黄昏(1972)
20.紅いコーリャン(1989)
(キネマ旬報1990年8月下旬号より)
「へぇ、1位は『E.T.』ですか」
「スティーヴン・スピルバーグは80年代ベスト監督においても1位に選出されている。やはり80年代といえばスピルバーグ印が映画界を牽引した10年ということになるんだろう」
「あれっ、『1900年』とか『ブリキの太鼓』とか『ミツバチのささやき』とか、70年代の映画がずいぶん混じってますよ」
「この時は『80年代に公開された映画』が対象だからね。でも欧米の巨匠たちに混じって、ホウ・シャオシェンやチャン・イーモウらアジア勢がランクインしているのが要注目だ」
「で、これが今年のベスト・テンではどうなったんですか」
「なんとこうなった」
2018年選出 1980年代外国映画ベスト・テン
1.ブレードランナー(1982)
2.ストレンジャー・ザン・パラダイス(1984)
3.バック・トゥ・ザ・フューチャー(1985)
3.非情城市(1989)
5.E.T.(1982)
5.男たちの挽歌(1986)
5.動くな! 死ね! 甦れ!(1989)
5.友だちのうちはどこ?(1987)
5.最前線物語(1981)
10.グロリア(1980)
10.ニュー・シネマ・パラダイス(1988)
10.ブルース・ブラザース(1980)
13.エル・スール(1983)
13.カリフォルニア・ドールス(1981)
13.恐怖分子(1986)
13.ラルジャン(1982)
17.ファニーとアレクサンデル(1983)
17.緑の光線(1986)
17.未来世紀ブラジル(1985)
20.シャイニング(1980)
20.スタンド・バイ・ミー(1986)
20.ブルー・ベルベット(1986)
(キネマ旬報2018年12月下旬号より)
「おおっ、『ブレードランナー』が10位から1位に大躍進!」
「リドリー・スコットの『ブレードランナー』はそもそも1982年の年間ベストテンでは25位だった作品だからね。ちなみにその年の1位は大ヒット作の『E.T.』だ。長い月日が経つことによって、その影響力の大きさ、作品の奥行きの深さが認められ、ついに80年代の『最高傑作』へと評価が改められた、というわけだ」
「去年は『ブレードランナー2049』という続編まで製作されたので、余計に1作目の存在感が浮上してきたのかもしれませんね」
「私としては、正直『ブレードランナー』も『ストレンジャー・ザン・パラダイス』も魅力がもうひとつ掴めない作品なのだが」
「ハイ、余計なことは言わないで。それにしてもカネフスキー『動くな! 死ね! 甦れ!』やキアロスタミ『友だちのうちはどこ?』は80年代の作品だったのですねぇ。てっきり90年代なのかと」
「公開されたのが90年代だから、当時の空気といっしょに記憶してしまいがちだけど、今回は『80年代に製作された映画』が対象なんだね。ホウ・シャオシェンは、90年のベストで選ばれた2作が消え、代わりに『非情城市』が堂々3位にランクインしている。票が集中するに足る代表作が登場した、ということだね」
「それにしてもロバート・ゼメキスの『バック・トゥ・ザ・フューチャー』とジョン・ウーの『男たちの挽歌』がベスト5入りというのもびっくりしました」
「共に80年代を代表する娯楽作品だが、投票したのは当時若者だった選者なんだろう。若いころに衝撃を受けたエンターテインメントというのは、生涯忘れがたいものだもの。『ブルース・ブラザース』や『スタンド・バイ・ミー』もランクインしてるしね」
「香港映画がランクインするならジャッキー・チェンだと思っていたので意外でした」
「代わりに『ダイ・ハード』が圏外に去ったのはどうしてかな? 89年度のキネ旬1位を獲得したアクション映画なのに」
「その後4本も作られた続編の出来が足を引っ張ったのかもしれませんね。しかしサミュエル・フラーの『最前線物語』がこんなに上位に来たのも驚きです」
「フラー、カネフスキー、キアロスタミ、カサヴェテス、アルドルッチ、このあたりの評価と人気の高さについては、それぞれの作品の強さはもちろんのこと、蓮實重彦の布教活動の成果、という気もしなくもないな」
「それにしちゃヴィム・ヴェンダースが影も形もありませんが」
「これは私も意外だった。『パリ、テキサス』と『ベルリン・天使の詩』は共に80年代を代表する作品だと思うのだが、なぜか28年前から変わらず圏外だ。ジム・ジャームッシュの『ストレンジャー・ザン・パラダイス』が変わらぬ人気を得ているのとは対象的だね」
「まぁ、当時キネ旬1位を獲得した『ソフィーの選択』や『アマデウス』、『ワンス・アポン・ア・タイム・イン・アメリカ』も共に28年前から圏外ですからね。立派な作品とは認めるけど、こうしたイベントで個人的に応援する気にはならない、ということなのかしら」
「タルコフスキーも入ってないしね。そう考えるとイングマール・ベルイマンの『ファニーとアレクサンデル』の人気はしぶといな」
「今年、生誕100年でひさびさに上映されたのも影響してるかもしれません」
「キューブリックも『フルメタル・ジャケット』が消え、代わりに『シャイニング』が票を伸ばしている。この辺りの人気の移り変わりも面白いね」
「こうなると日本映画の方も気になりますね」
「では、1990年選出の80年代日本映画ベストから見てみよう」
1990年選出 1980年代日本映画ベスト・テン
1.ツィゴイネルワイゼン(1980)
2.泥の河(1981)
3.ゆきゆきて、神軍(1987)
4.家族ゲーム(1983)
5.となりのトトロ(1988)
6.お葬式(1984)
7.戦場のメリークリスマス(1983)
8.台風クラブ(1985)
9.細雪(1983)
10.ニッポン国 古屋敷村(1982)
11.遠雷(1981)
12.転校生(1983)
13.風の谷のナウシカ(1984)
14.黒い雨(1989)
15.乱(1985)
16.影武者(1980)
17.竜二(1983)
17.どついたるねん(1989)
19.の・ようなもの(1981)
20.海と毒薬(1986)
20.コミック雑誌なんかいらない!(1986)
(キネマ旬報1990年9月上旬号より)
「なるほど、正直なところずいぶんバランスのいい並びに見えますけど」
「まさにキネ旬らしいランキングだよね。80年代ベスト監督には相米慎二が選ばれている」
「小栗康平、森田芳光、伊丹十三、宮崎駿、大林宣彦という80年代登場組に、鈴木清順や大島渚などのベテランが気を吐き、市川崑、黒澤明ら巨匠も健在だった時代ですね」
「これが、2018年ではこうなった」
2018年選出 1980年代日本映画ベスト・テン
1.家族ゲーム(1983)
2.ツィゴイネルワイゼン(1980)
2.ゆきゆきて、神軍(1987)
4.戦場のメリークリスマス(1983)
5.その男、凶暴につき(1989)
6.台風クラブ(1985)
7.転校生(1983)
8.風の谷のナウシカ(1984)
9.Wの悲劇(1984)
10.どついたるねん(1989)
10.となりのトトロ(1988)
12.さらば愛しき大地(1982)
12.鉄男(1989)
12.泥の河(1981)
15.ションベン・ライダー(1983)
15.ニッポン国 古屋敷村(1982)
17.ウンタマギルー(1989)
17.遠雷(1981)
17.人魚伝説(1984)
(キネマ旬報2019年1月上旬号より)
「なんと、1位は森田芳光の『家族ゲーム』になりましたか」
「90年度のベスト・テンでも、読者選出の方では『家族ゲーム』が1位だったんだよ。鈴木清順の『ツィゴイネルワイゼン』のカリスマ性や原一男『ゆきゆきて、神軍』の衝撃力は依然高いが、今振り返ると、森田の斬新なホームドラマの方が、80年代という時代を的確にとらえていたのかもしれない」
「小栗康平の『泥の河』が順位を下げる一方で、大林宣彦の『転校生』が順位を伸ばしていたり、面白いですね。突然の急浮上としては北野武『その男、凶暴につき』、澤井信一郎『Wの悲劇』、塚本晋也『鉄男』、柳町光男『さらば愛しき大地』があります」
「北野武と塚本晋也はその後、日本映画界を代表する監督に成長したので、その出発点を重視したい、という投票者が多かったんじゃないかな。『どついたるねん』の阪本順治もそのパターン。『Wの悲劇』は前回39位、『さらば愛しき大地』は前回23位だったので、やはりリアルタイムで観て、衝撃を受けた世代から票を集めることになったんだと思う」
「まぁ、角川映画から一本選ぼうと思えばそりゃ『Wの悲劇』になりますよ」
「そう? 私なら大林の『時をかける少女』か和田誠の『麻雀放浪記』」
「一方で、黒澤明や市川崑、今村昌平らはさすがに姿を消しましたね。しかし、『戦場のメリークリスマス』は強いなぁ」
「『戦メリ』の人気は私にもよくわからないが、大島渚のスタイルが80年代らしい形に大きく変化した点で重要視されているのかな。もうひとつ、高嶺剛の『ウンタマギルー』や池田敏春の『人魚伝説』のような一種のカルトムービーに票が集まったのは、2018年には見かけなくなったタイプの作品だから、なのかもしれない」
「80年代日本映画の『顔』といえば伊丹十三も外せない存在だと思うのですが、圏外に去りましたね」
「これは残念だねぇ。『お葬式』、『タンポポ』、『マルサの女』の3作は、まさに80年代を象徴する重要作だと思うのだけど。滝田洋二郎の『コミック雑誌なんかいらない!』も、もっと順位が上がるかと思っていたらそうでもなかったので意外だ」
「しかし二つのランキングを見比べると、やはり80年代は相米慎二と宮崎駿の時代だった、と言えそうですね」
「じつは私、1位は『ナウシカ』か『トトロ』じゃないかと内心予想していた。ちょっと票を食い合ってしまったのかな。それにしても、相米慎二、森田芳光、伊丹十三が故人となった今、宮崎駿が今も新作製作中というのは喜ぶべきことだね」
「いやぁ、山田洋次もクリント・イーストウッドも健在ですよ」
「たはっ、そうでした。では最後にキネ旬本誌を読む前に選出しておいた、極私的1980年代ベストテンを挙げておこう。順位はいいかげんです。ほぼ思いついた順」
<外国映画>
1.太陽の帝国(1987)
2.未来世紀ブラジル(1985)
3.カメレオンマン(1983)
4.ロジャー・ラビット(1988)
5.バック・トゥ・ザ・フューチャー(1985)
6.プロジェクトA(1983)
7.フルメタル・ジャケット(1987)
8.旅立ちの時(1988)
9.バベットの晩餐会(1987)
10.フィツカラルド(1982)
<日本映画>
1.ドラえもん のび太の宇宙開拓史(1981)
2.ツィゴイネルワイゼン(1980)
3.マルサの女(1987)
4.うる星やつら2/ビューティフル・ドリーマー(1984)
5.天空の城ラピュタ(1986)
6.コミック雑誌なんかいらない!(1986)
7.東京裁判(1983)
8.爆裂都市 BURST CITY(1982)
9.乱(1985)
10.ゴジラVSビオランテ(1989)
「封切で観た作品とレンタルビデオで観た作品がごちゃ混ぜですね」
「一人で映画を観に行くようになったのが80年代の半ばで、同時にレンタルビデオが大流行した時期でもあったのね。我々の世代の映画体験はどうしてもビデオやテレビ放送で観たものが混じってしまう。今年、『爆裂都市 BURST CITY』をNFAJの上映で観られたので、いちおうすべてスクリーン観賞はしてるけど」
「でも『カメレオンマン』は劇場で観てないでしょ」
「そういやそうでした。しかしウディ・アレンを外した80年代は考えられない。それに『カメレオンマン』はビデオ版の日本語吹替が良くできていて、本当にNHKで放送される海外ドキュメンタリー風に仕上がっていたんだよ。あれが忘れられなくてさ。Blu-rayで出してくれないかな」
「ロバート・ゼメキスが2本入ってますね」
「最初はエドワード・ヤンの『恐怖分子』を入れてたんだけど、やはり80年代に観た映画に限定しようと差し替えちゃった。私にとって80年代はゼメキスの時代です。文句あるか」
「いえ、べつに……。ただ、ジョン・ランディスやジョン・カーペンターに悪いな、と思って」
「80年代はもっとも多感な時期を過ごした時代だけど、はっきり言って不愉快な時代だったよ。『ネアカ』なんて流行語に代表される、虚飾の明るさに満ち満ちてさ。しかし振り返ってみると、あのいまいましい狂騒のおかげで、カルチャーの面においてはずいぶんと多様化をもたらしてくれた、という事実は確かにある。田舎の鬱屈した少年になんらかの刺激や世界の拡がりを与えてくれた作品群を並べてみました」
「30年後、2010年代の映画ベストを選んだらどんな並びになるでしょうね」
「そんなことを考えながら、今夜は実相寺昭雄監督のロッポニカ作品『悪徳の栄え』(1988)でもいっしょに観ようじゃないか。いやぁ、これも入れたかったんだけど観たのがだいぶ遅かったからさぁ」
「ご遠慮しておきます。そろそろ『明石家サンタ』が始まる時刻なので……。それではみなさん、メリークリスマス!」