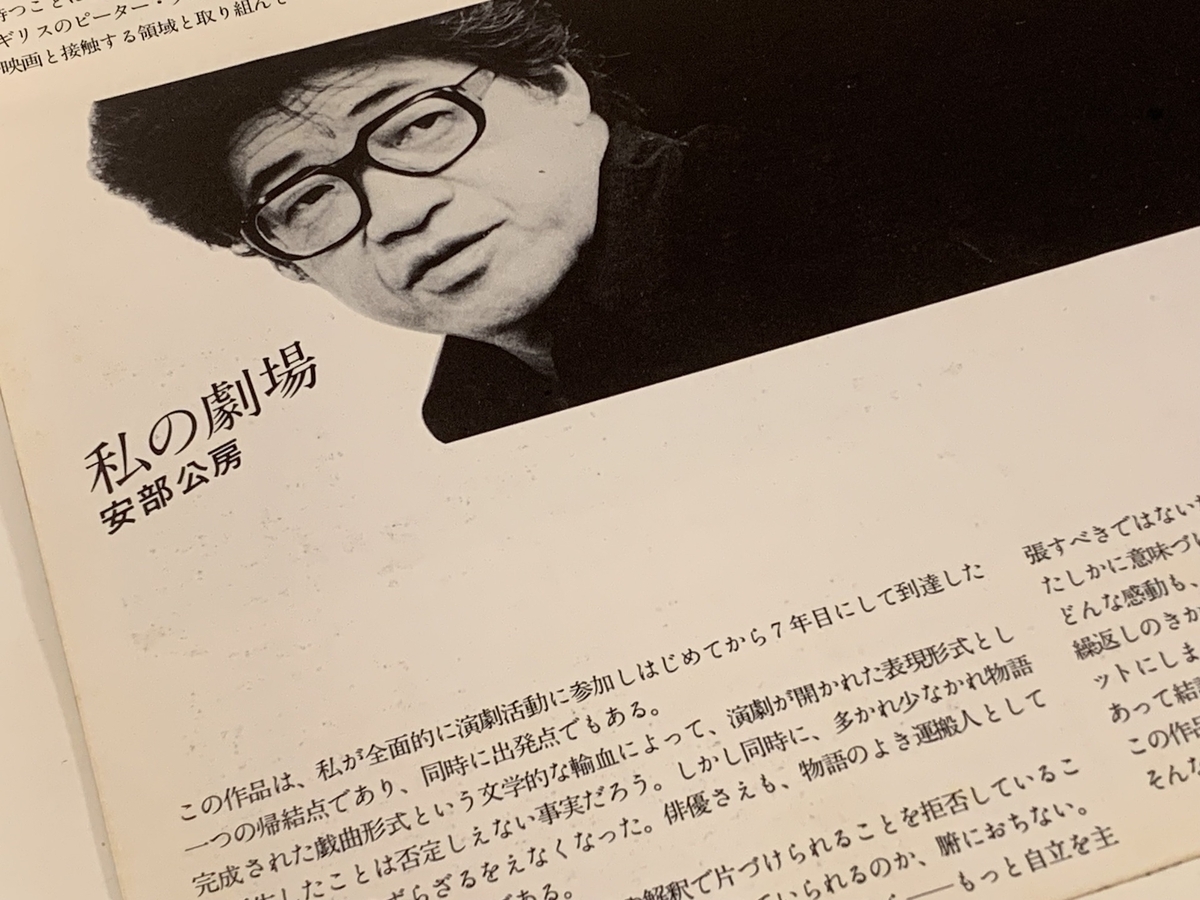シネマヴェーラ渋谷で「生誕百年記念・シネアスト安部公房」が開幕した。
なんといっても目玉となるのは安部公房が自ら監督した16ミリ短編『時の崖』(1971)と、ビデオ版『仔象は死んだ』(1980)の上映だろう。さっそく観てきましたよ。
今回初めてスクリーンで観ることができたのは、『時の崖』。井川比佐志演じるロートルボクサーの試合前(実時間)の独白と、ノックダウンされた後(10秒間の拡大)の意識の流れを描く31分。ゲストトークで石井岳龍監督が、「言葉による音楽」と評したが、まさに映像と音と台詞を組み合わせた一種の私的映像詩。これ、先行作品としては勅使河原宏監督・安部公房脚本・武満徹音楽による短編映画『白い朝』(1965)があたると思うが、『白い朝』は録音素材をもとに武満をミュージックコンクレートを編集、安部が台本を書いて、勅使河原が映像を撮るという共同作業だったそうで、極めてエレガントな仕上がりだった。一方、『時の崖』は安部が一人で指揮しているため、より乱暴で、どこか完成を拒否するような部分もある。
そもそも『時の崖』は、武満徹との共同制作によるラジオドラマ『チャンピオン』(1963)が出発点。ボクシングジムで録音してきたノイズやボクサーの呟きに、安部が紡いだ主人公の独白やセリフが構成されてゆく音響詩の傑作だった。これが「敗者による一人称」で展開する短編小説『時の崖』へと再構成され、さらに戯曲『棒になった男』の第二景における井川比佐志の独り芝居へと発展。その演技を記録するために、自主制作で撮られたのが映画『時の崖』だ。「同じネタで何回こすってんだよ!」、とツッコミたくなる向きもあろうが、ジャンルを横断しながらアイディアを「更新」させてゆくのが安部公房のスタイルである。
映画『時の崖』の製作は小説『箱男』の執筆と同時並行、映画の完成後、安部公房スタジオの第ゼロ公演というべき『ガイドブック』の稽古に入るので、まさに安部公房が70年代に向けて新たに羽ばたこうとしている時期にあたる。おそらく劇団運営が軌道に乗ったら、本格的な映画制作にも乗り出すつもりだったに違いない。
実は映画『時の崖』と映像版『仔象は死んだ』は、かつて私家版のビデオソフトが作られており、安部公房の葬儀で参列者に配布されている。私はそのビデオ版で観せてもらったのが初見だが、映像は全編白黒で統一されていた。
ところが勅使河原宏のエッセイ「監督誕生」を読むと、映画『時の崖』についてカラー映像のインサートによる効果を評価しているのである。この作品はパートカラーだったのか! はたして別バージョンが存在するのか、長いこと疑問だったのだが、今回の上映版を確認したところ、一瞬インサートされる、モデルの女性が映るCM風の映像がカラーだったことがわかった。私家製ビデオ版にもこの場面は残っているので、おそらく16ミリ原盤からビデオ製作のためにテレシネをかけた際にカラーが記録されなかっただけなのだろう。
このカラー映像、当時の本物のCMの一場面らしいのだが、安部公房としては「ボクシングの中継にCMが挿入されることのパロディ」を狙ったものと発言している。わかるか、そんなの。現在の観客にはあれがCMかどうかすら判別不能なので、「意味」を探してもお手上げだが、カラーの異質な映像が無意味に飛び込んでくることで、テンカウントの10秒間に駆け巡る、混沌した意識の象徴としては確かに効果的だった。
カラーが少し褪色してしまっていたのは残念だ。

今回の上映素材は『時の崖』がBlu-rayで、もう一本の『仔象は死んだ』はデジタルベーカムとのこと。いつの間にかデジタル上映用のコピーが製作されたらしい。イベント集客用もよいが、できればパッケージソフトも発売してほしい。
『仔象は死んだ』は原盤がビデオ素材で、上映会用の16ミリも作られていたようだが、安部としてはビデオソフトでの発売の意図があったようだ。後期の安部公房スタジオは集客面で苦戦していたと聞くが、ビデオソフトの形で作品が流通すれば、劇団が描くスタイルが知れ渡り、新たな観客を発掘することができるのではないか、という期待があったのだろう。映画のビデオソフトが普及し始めた当時にこの発想。しかも、ただ公演を記録するのではなく、ソフト用にテレビスタジオで収録し直し、編集での合成処理や音響効果も工夫した特別バージョンを作るという凝りよう。早すぎた「ゲキシネ」である。

じつは『仔象は死んだ』は上演形式がまとまった時点で、雑誌「新潮」に掲載するための台本が作成されている(全集26巻に収録)。私は古本で手に入れた「新潮」で先に台本を読んでおり、その上でビデオを観せてもらったので、「なるほど、こういうパフォーマンスだったのか〜」という感心が先に立ってしまい、ちょっともったいないことをしたと後悔している。今回シネマヴェーラにつめかけた観客と同じに、作品を観て「なんじゃ、こりゃあ〜!」という困惑を味わいたかった。
映像版『仔象は死んだ』は冒頭に「肉体+音+言葉=イメージの詩」とタイトルが出るが、まさに「夢が見た夢の世界」を描く映像詩。明確なストーリーは存在せず、『箱男』や『笑う月』に断片的に描かれたイメージがパフォーマンスとなって再現されてゆくが、クライマックスに「裁判」が用意されているあたりは『S・カルマの犯罪』への回帰というか、安部が好んだ『不思議の国アリス』バリエーションのように見えなくもない。
ビデオ版『仔象は死んだ』の試写に訪れた淀川長治は、見ながらこんなメモを取ったという。
(タイトル。いい!)(マーサ・グラハム)(舞踊詩)(セット・デザイン)(衣装デザイン)(カラー)(モダン・バレエ)(アバンギャルド)(ドイツだ)(ニューヨークだ)(どうして、これは日本だぜ)(超モダン)(やくどう)(映画美術的やくどう)(すごい創造、(本物、ニセモノ、これは本物)(アニメじゃ出せまい。この舞台ファンタジィのすごさ!)(SFの宇宙映画をのりこえたこのファンタジィ)(演出。フリツケ)(無限の詩)(文句を考える必要なし)(しかし、このコトバ……弱者への愛にはいつも殺意がこめられている)(リンゴをグシャリと齧る白面の二本棒のごとき2人の男)(このコトバ……こわい)(白布……ふくれる……しぼむ)(白布)(白布)(この白布のひろがり)(いったい誰が考案したか)(白布、海になる)(白布、雲になった)(画面が呼吸しとる)(呼吸だ)
「無限の流動美-(影と光)の中に-」より
興奮が伝わってくるではないか。
「このパフォーマンス、動ける肉体さえあれば俳優は誰でも代替可能なのでは? 代替不能な存在としているのは山口果林だけ」
「『俳優は意味の運搬人になってはいけない』と書いていながら、ここでは俳優が安部公房のイメージの運搬人になってしまっているように見える」
との疑問を呈していた。これは桐朋学園の演劇課の教員として安部と親しかった大橋也寸も『仔象は死んだ』に対しては同じような批判を書いていたので、演劇人には共通して抱く不満らしい。
しかし一方で鴻上尚史は「仲代達矢と田中邦衛と井川比佐志なんて主演級を揃えて一メンバーとして扱う舞台、やれったって普通できませんよ!」とも語っていて、安部公房もまさに「新劇の大スター」を抱えたままでは、いずれ旧来の新劇イメージの中で理想が窒息することに気づいたのかもしれない。
安部公房スタジオは1975年に『ウエー・新どれい狩り』という舞台を上演しており、ここにはベテランの新劇スターはあえて出演させず、安部公房子飼いの桐朋学園出身の俳優たちが中心となった公演だった。16ミリでゲネプロを撮影した映像を観たかぎり、普通の新劇作品とほぼ変わらない舞台であり、演技もいわゆる型芝居が目立つ。しかも俳優個人の存在感や表現力が乏しいので、安部のロジカルな台詞のやりとりが停滞し、「退屈な卒業公演」という印象さえあった。「心理ではなく生理からアプローチした演技法」とのたまう安部システムの成果がいまいちわからん、という批判は当時の劇評からもうかがえる。
そんな模索を経た後期の安部公房スタジオは、「イメージの展覧会」を中心とする、より抽象性の高い舞台を志向するようになる。「俳優の名演技」にも、「ストーリーの面白さ」にも頼らない、ましてやアングラ的なヒステリー状態や観念先行の深刻ぶった世界を見せるわけでもない、それでいて芸術的で娯楽性も感じられるショー。俳優たちはそれぞれ無名で存在感がなくても、サーカス団員に匹敵する肉体を持ち、ある状況になると、無名の顔が突如「有為」な存在に変質する。『仔象は死んだ』の後半、スタジオの地下から緑のネットをまとって奇声をあげる虫みたいなのが登場するが、あれは若き日の浅野和之(当時は加藤斉孝)だ。それまでアンサンブルの一員だった彼が、あのパフォーマンスを始めた瞬間、やはり場面をさらってしまう。ああいうアイディアも、決して安部一人で思いついたのではなく、日々の肉体訓練と稽古による共同作業で生み出されたものだと思う。
安部公房スタジオが1980年代も存続したら、いずれはシルク・ドゥ・ソレイユのような集団になっていたかも……などと思った『仔象は死んだ』再見であった。